「教育=RPG説」をもとに、子どもの成長と、大人が果たすべき役割について考えてみたいと思います。
この記事では子供の教育に対する考え方に迷っている人に向けて、また教育に携わる人に向けて、今の〝沼〟を抜け出せるように、ゲームに例えて、私の実体験とともに教育について解決の手がかりを得られるようにしたいと思っています。最後までお付き合いください!
勝てないチームと「主体性重視」の矛盾
息子が通っているスポーツクラブは、子どもたちの主体性を大切にする指導を重視されています。
- 子ども同士で声を掛け合う
- 楽しさを重視し、うまい子もそうでない子も同じように混ざって練習する
- 指導者は技術的な指導はほぼしない
- 自分たちで良くなるために、自ら気づきチャレンジさせたい
- 楽しくサッカーすることが大事
「いいと思う、なにも問題ないように思うけど。。。」
と思いませんか?私もそう思っています。
それでも、低学年のときは勝てていましたが、最近では実際の試合では勝てません。
そして、上手な子たちは次々に他のチームに移籍してしまう。
なぜなのか?と思って練習を観察してみると、あることに気づきました。というより、気づいていたけど蓋をしていたと言った方が正確でした。
- ボールタッチ、トラップ、蹴り方、奪い方など、「基礎基本」の習得に大きな差がある
- 練習試合が多く、基礎練習の時間が極端に少ない
- だからチームとしての連携や土台が育っていない
つまり、「主体的にやらせる」前提であるべき“土台”が整っていない状態で、いきなり戦わせてしまっている印象を受けてしまうのです。
「型」と「自由」をめぐる、かつての自分の現場体験
私は以前、運動系の部活動で、中学生たちの指導に携わっていました。指導員という名目でしたが実態は
その競技では、いわゆる「型」の習得がとても重要でした。
基本的な構え、足の運び、打撃の加え方、そして礼儀作法――
どれも見た目は地味で、動きとしては単純で、最初のうちは「なんでこれを何度も繰り返すの?」と子どもたちが疑問に思うような練習ばかりです。そこには正直言って〝楽しみ〟というものはなかったと思います。
けれど私は、その型を、繰り返し、繰り返し、やらせてきました。私が不在の時も最高学年に確実に実行させました。
それは、“きまり”を教えたかったからではありません。
むしろ逆で、その型が身体に入ってはじめて、自由が始まると信じていたからです。
当時の教えたるもの「工夫はしなさい」「考えて練習しなさい」「頭を使いなさい」という指導でした。自分自身うまく結果が出せなかった時期に、その答え探しにさらに迷走し、もがいていました。私のようなタイプには、〝考える材料〟をたくさん示して教えて欲しかったなと客観的に見られるようになった数年後に思ったのです。
だから、私は指導者になったら、何度も基本動作をくり返し、加えて工夫の例を実際にやってみせ、やらせてみせたのです。子供達は見事に吸収し、工夫の材料の糧としていました。
そんなある日、ふと、一人の生徒の動きが変わったことに気づきました。
それまで教えた通りの動きしかできなかった子が、自分の間合いを自分で測り、自分の判断で入り、自分なりの“技”を出した瞬間でした。
その姿は、今思えばまさに“自分で考えて動く”という教育の理想そのものでした。
このとき私は、改めて実感したのです。
「自由」とは、土台があるからこそ発揮されるもの。
型を知っているからこそ、型から離れられる。
教育においてもまったく同じだと思っています。
自己決定を重んじたいからこそ、“判断の材料となる型”を身につけることが必要不可欠なんです。
それがないまま自由を与えてしまえば、ただの放任になってしまう。
この指導経験は、私の中にずっと残っていて、今でも何かに迷ったとき、いつもこの原点に立ち戻っています。
ファイナルファンタジーの主人公を思い出す
教育について話しているときに、私はふと昔夢中になったRPG『ファイナルファンタジー』を思い出しました。
あのゲームの主人公たちは、最初はとても弱い。
スライムすら倒せないレベルからスタートして、地道に戦って経験値を積み、少しずつ強くなっていく。
新しい武器や防具を手に入れ 魔法を覚え 仲間を増やし 戦略を学びながら、最終的にはボスを倒す
子どもたちの成長って、まさにこれと同じじゃないかと気づいたんです。
基礎がなければ、主体的に動けない。
「好きにやっていいよ」と言われても、そもそも動く力が備わっていなければ、自由すら苦痛になってしまう。
大人は「名もなき支援キャラ」でいい
RPGには、戦わないけれどプレイヤーを支えてくれる“名もなき支援キャラ”がたくさん登場します。
- 村の道具屋
- 回復してくれる宿屋のおばさん
- 次の目的地を教えてくれる老賢者
彼らの存在は地味だけど、確実にプレイヤーの冒険を支えてくれています。
教育においても、私たち大人はそれでいいんだと思うのです。
環境を整え 基礎を教え 成功も失敗も経験させ 必要なときだけそっと助ける
子どもが「自分の人生の主人公」として動き出すまで、そばで見守る“案内人”でいること。
それこそが、教師や親としての真の役割なのかもしれません。
書いていて気づいた、自分自身の矛盾
でも実は、この記事を書きながらひとつの矛盾に気づきました。
私はよく、「子どもに失敗させよう。そこから学ばせよう」と言っています。
なぜなら、
- 失敗を人のせいにしない姿勢を持ってほしい
- 自分で決めてやったことなら、失敗しても納得できる
- 自己決定が積み重なることで、自己肯定感が育つ
…と信じているからです。
だけど同時に、「基礎・基本はしっかりやらせたい」とも思っている。
つまり、“やらせる”という関与と、“任せる”という放任のあいだで、揺れているんです。
教育とは、矛盾とともに進むもの
この矛盾に気づいたとき、「自分は教育者として失格なんじゃないか」と思いました。
でも、今は少し違う考え方をしています。
- 揺れるからこそ、子ども一人ひとりに合わせて考えられる
- 正解がないからこそ、問い直し続けることができる
- ブレるからこそ、心から悩み、真剣に向き合える
教育は、「揺らぎ」を抱えたままでいい。
それはむしろ、誠実さの証なんじゃないかと、今は思います。
あなたにとっての「教育」は?
子どもに「自由」を与えたい。でも「基礎」も教えたい。その矛盾を抱えながらも、一歩ずつ前に進む
あなたにとっての「教育」は、どんな物語ですか?
今日もまた、子どもたちは経験値を積んでいます。
私たち大人もまた、自分自身の教育観をレベルアップさせていけたらいいですね。
この記事が気に入ったら、スキ・フォロー・コメントで応援していただけると嬉しいです。
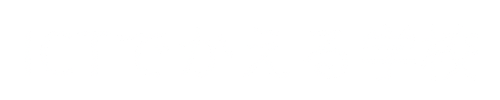



コメント