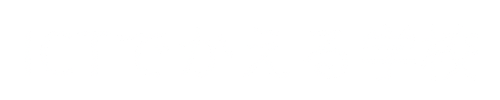私自身、長年にわたり学校現場で子供たちと接してきた教師であり、一方で親としても日々悩みながら子供の成長を見守ってきました。現代はデジタル技術が飛躍的に進歩し、子供たちの生活にスマートフォンやタブレットが欠かせない存在となっています。しかし、その便利さの裏には、子供がまだ十分に判断力を持たず、様々なトラブルや危険に巻き込まれる可能性も秘めています。私が実際に学校や家庭で経験してきたこと、また子供との関係を通して得た知見をもとに、今回は「子供に携帯やタブレットを持たせる際のルール作り」について、温かい親心と教師としての現実的な視点を交えながらお話ししたいと思います。
ルール作りの基本

まず、子供にデジタル機器を持たせる際に最も大切なのは、「ルールを明確にする」ということです。多くの保護者が思い浮かべるのは、ただ単に「使ってよい時間」や「場所」の制限かもしれません。しかし、私が実践しているのは、あえて抽象的な約束ごとを設定し、子供自身にその意義を考えさせ、納得させる方法です。例えば、我が家では中学生に上がる直前に渡したデジタル機器について、下記の9項目は我が家での基本ルールとして子供と合意形成をしています。これにより、子供は自分の行動に対する責任を自覚し、ルールを破った場合には当然の結果が待っていることを理解するのです。
- 学校での学習やデジタル教育のための使用に限定する。
- 健康を害する使い方はしない。
- 他人を傷つけるような使い方は禁止する。
- 家庭内ではリビングなど共用スペースで使用する。
- 家族や他者が不快に感じる使用は控える。
- 携帯端末はあくまで親からの貸与品であると認識する。
- 親は定期的に中身を確認し、責任を持つ。
- 使用に関して疑問が生じたらすぐに相談する。
- 自由には必ず責任が伴うという信頼関係を築く。
これらのルールは、単なる形式ではなく、実際に子ども自身に署名させる「契約」として取り交わすことで、互いの認識のズレを防ぎ、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。正直なところ、子供が「そんなことするわけがない」と無邪気に考えるとしても、いざ問題が起こった際には「言った・言わない」の揉め事になるリスクは否めません。実際、私自身の家庭でも、Suicaの残高が出先で切れてしまい、やむを得ず非常時に備えてキャッシュレス決済の設定をしておいたことがあります。勝手に使うことはしないという約束のもと、そのまま子供に任せた結果、数万円の使い込みが発生した経験があります。原因は子供のストレスや好奇心にあったということでした。それにしても、その事実をしっかりと伝え、返済を求めることで、子供に金銭管理の大切さや、自由には責任が伴うという現実を学ばせる機会となりました。
技術的対策と管理方法

ルール作りと並行して、技術的な対策も欠かせません。スマートフォンでは、AppleのiPhoneの初期設定時に「子ども用モード」を選択し、ファミリー設定を施すことで、スクリーンタイムの管理やアプリの追加・削除の制限、さらにはSafariなどの標準ブラウザの非表示といった機能を活用できます。これにより、子どもが不用意に不適切なアプリをインストールしたり、危険なサイトにアクセスするリスクを大幅に低減できます。
けます。
【iPhoneでの具体的な設定方法】
iPhoneは「子供用」で設定することが最初のステップです。次の設定をしておきましょう。
ファミリー共有の設定
• 詳細な手順は、iPhoneのファミリー共有でお子様のデバイスを設定するをご覧ください。
• スクリーンタイムの設定
• 詳しくは、お子様のiPhoneやiPadでペアレンタルコントロールを使うを確認してください。
• コンテンツとプライバシーの制限
• 手順は、お子様のiPhoneやiPadでペアレンタルコントロールを使うをご確認ください。
お子様にスマートフォンを持たせる際、各携帯キャリアが提供しているフィルタリングサービスを活用することで、安心・安全な利用環境を整えることができます。以下に、主要キャリアのフィルタリングサービスをご紹介します。
NTTドコモ:あんしんフィルター for docomo
NTTドコモは、「あんしんフィルター for docomo」を提供しています。このサービスは、お子様の年齢に応じてインターネットやアプリの利用を制限し、不適切なサイトやアプリへのアクセスを防ぎます。また、利用時間の制限や位置情報の確認など、保護者が安心して管理できる機能も備えています。
• 詳細情報: フィルタリングサービス | サービス・機能 – NTTドコモ
au(KDDI):あんしんフィルター for au
auは、「あんしんフィルター for au」を提供しています。このサービスでは、有害情報のブロックだけでなく、スマートフォンの利用時間帯の設定や、居場所の確認も可能です。お子様の年齢に合わせて、フィルタリングレベルを「小学生」「中学生」「高校生」「高校生プラス」の4段階から選択できます。
• 詳細情報: サービス詳細 | あんしんフィルター for au:サービス・機能 | au
ソフトバンク:あんしんフィルター
ソフトバンクは、「あんしんフィルター」を提供しています。このサービスは、お子様を不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンを利用できるようサポートします。ウェブサイトやアプリの利用制限、利用時間の管理、位置情報の確認など、多彩な機能を備えています。
• 詳細情報: あんしんフィルター | スマートフォン・携帯電話 – ソフトバンク
ワイモバイル:あんしんフィルター
ワイモバイルも、「あんしんフィルター」を提供しています。お子様が安全にスマートフォンを利用できるよう、不適切なサイトやアプリの利用を制限する機能を備えています。また、利用時間の管理や位置情報の確認など、保護者が安心して見守るための機能も充実しています。
• 詳細情報: あんしんフィルター – 格安SIM・スマホはワイモバイルで
各キャリアのフィルタリングサービスを活用することで、お子様のスマートフォン利用を適切に管理し、安心・安全な環境を提供できます。サービスの詳細や設定方法については、各キャリアの公式サイトをご確認ください。
また、パソコンに関しては、Microsoftの「Family Safety」やGoogleの管理ツールを利用して、利用時間の制限やアプリのダウンロード制限、ブラウザのプライベートモードの使用禁止など、包括的なセキュリティ対策を実施しています。こうした技術的な管理は、学校でのタブレット利用と連動させることで、家庭と学校の双方から子どもたちのデジタルライフをしっかりとサポートするための重要な手段となっています。
けます。
【Windowsパソコンでの設定方法】
パソコンでも同様に制限をかけることが大切です。
• Microsoft Family Safetyの設定
• 詳細は、Microsoft Family Safety の概要をご覧ください。
親子間のコミュニケーションと信頼関係

ここで大切なのは、子供に対してただ一方的にルールを押し付けるのではなく、親子でしっかりと話し合い、その意味を共有することです。私もまた、子供との会話の中で「なぜこのルールが必要なのか」「自由には必ず責任が伴う」といった基本的な考え方を繰り返し伝えてきました。その結果、子供自身も自分の行動について深く考えるようになり、ルールを破った際には自ら反省し、再び正しい道を選ぶようになると感じています。こうしたやりとりは、時には厳しい言葉を交わすこともありますが、親子間の信頼関係をより一層深める大切なプロセスだと信じています。

家庭だけでなく、学校や保護者さんと情報を共有し合い、横の繋がりを見通し良くしておくことも、子どもの健全な成長を支える上で非常に有効です。保護者同士が互いの経験を語り合い、成功事例や失敗談を共有することで、一人ひとりの家庭での取り組みがより充実したものになりますし、子供同士の使い方の共通認識が図れるよさもあります。結果として子どもたちの未来に対する大きな投資となるのです。
デジタル社会と未来への投資

現代社会においては、SNSや動画共有サイト、チャットアプリなど、子供たちが容易に情報にアクセスできる環境が整っている一方で、外部からの悪影響やトラブルも増加しています。私自身、教師として、また親として、子供たちが知らず知らずのうちに有害な情報に触れたり、誤った価値観を身につけてしまう危険性を強く感じています。そのため、家庭でのルールや技術的な制限に加え、子供自身が情報の正しい取捉方法を学ぶ「デジタルシチズンシップ教育」も、非常に重要な課題として取り組んでいるのです。子供たちが自ら考え、判断し、そして責任を持って行動できるようになるためには、日々の生活の中で大人が手本を示し、共に学び成長していく姿勢が必要です。
まとめ

デジタル機器はあくまで「道具」に過ぎず、その真価は使う人間の心にかかっています。その心を子供に身につけさせることが最も大切なICT教育なのです。私たち大人が、教師としても親としても、日々の生活の中で示す行動や態度が、子どもたちの未来をより良いものへと導くのです。子供に言うことは少なくとも子供の前でしない、自分ができないことは子供には言えないと言うことをどうか心に留めておきたいものです。子供は言うことは聞きませんが、親のやることは真似しますので。
この記事が、少しでも皆様の参考となり、家庭や学校での子どもとの接し方に新たな気づきをもたらすことを心より願っています。デジタル時代の中で、子どもたちの未来を守るための努力は、決して一人の力では成し得ません。教師、親、そして地域全体が協力し合い、互いの知恵と経験を共有することで、子どもたちにとって安全で温かい環境を築いていくことができるはずです。
【おまけ】
システムのセキュリティでガチガチにすると、子供同士で情報交換をしてその抜け道を見つけます。
例えば時間をずらしてスクリーンタイムを回避したり、再起動を数回繰り返すことでスクリーンタイムをオフにできたりする裏技などです。
YouTubeはもちろん、LINEVOOM、ラインアカウントから登録したらコミュニティ内での動画閲覧、画面収録を使って本体に保存したコンテンツ閲覧、各種設定のカスタマイズなど次々と見つけてから見つけてくる。「はい、しってるよ。残念、それ知っちゃったのね。」と想定内だという余裕を見せた対応がお勧めです。
制限は端末自体にかけられるものと、アプリごとににかけられるものがあります。それぞれ子供の実態に応じて、はじめはガチガチで最低限しか使えないくらいから少しずつ緩めていくことをお勧めします。