
新入生説明会の準備を進めている先生方も多いでしょう。
「もっと事前に準備しておけばよかった…」
「説明したのに登録していない保護者が多い…」
そんな後悔をしないために、事前準備で説明会後の負担を減らすことが大切です。
新年度の4月は、保護者も子どもも、そして先生方も慌ただしくなります。
やるべきことが山積みになるこの時期に、少しでも負担を減らすために、説明会でできることはその場で終わらせる工夫が必要です。
✅ 新入生説明会で準備しておくべき5つのこと
- 連絡アプリの登録をその場で完了させる
- 地区班の確認を確実に行う
- 幼児対策(退屈させない工夫)を用意する
- 結核関係の書類をできる限り事前回収する
- 個人情報の回収は可能な限りオンライン化する
これらを押さえておくと、説明会後の手間を減らし、
年度初めのバタバタを最小限に抑えられます。
1. 連絡アプリの登録は「その場で完了」
保護者との連絡手段を確立することは最優先事項です。
特に最近は、紙のプリントだけでは情報が届かないことが増えています。
そのため、新入生説明会で連絡アプリの登録を済ませてしまうのが最も効率的です。
✅ やるべきこと
- 仮のクラス・学年を設定し、事前登録を促す。
- QRコードを印刷して掲示し、その場でスキャンして登録してもらう。
- スライドを使って登録手順を視覚的に説明する。
- 「この場で登録してください」と時間を確保する。
- 登録完了を確認する仕組みを作る(受付で画面提示など)。
- 登録がわからない人向けに、サポートスタッフを配置する。
✅ ここがポイント!
→ 「後で登録してください」ではなく、説明会の場で登録完了を目指す!
2. 地区班の確認は「対話できる場」を作る
「どの地区班に所属するのかわからない」
これは、新入生が入学してからよく発生する問題です。
後から個別対応すると時間がかかるため、説明会で確実に解決しておくことが重要です。
✅ やるべきこと
- 受付に地区班のGoogleマップ・白地図を拡大して掲示する。
- リボンやシールなどで、地区ごとに色分けする。
- 地区ごとのグループで顔合わせの時間を設ける。
- 「わからない方は受付でご相談ください」と案内する。
✅ ここがポイント!
→ ただマップを掲示するだけではなく、実際に対話できる場を作る。
3. 幼児対策を万全にする

新入生説明会には、必ず小さな兄弟姉妹を連れてくる保護者がいます。
幼児が退屈すると、説明会の進行がスムーズに進まなくなることも…。
✅ やるべきこと
- 簡単なアクティビティやおもちゃを用意する。
- 子ども向けのビデオを流すコーナーを作る。
- 可能なら、ボランティアの児童に幼児のお世話をお願いする。
✅ ここがポイント!
→ 幼児が静かに過ごせる環境を作ることで、説明会の進行がスムーズになる!
4. 結核関係の書類は「事前回収」が理想
年度初めは、学校も保護者もやることが多い時期です。
書類の提出が後回しになり、未提出が発生しやすくなります。
✅ やるべきこと
- 説明会で提出してもらえるように、事前に案内する。
- その場で記入できる時間を設けると未提出が減る。
✅ ここがポイント!
→ 4月の負担を減らすために、説明会の時点でできる限り回収する。
5. 個人情報の回収はオンライン化が理想
年度初めは、個人情報の紛失が最も多い時期です。
紙の管理は手間がかかる上に、紛失のリスクも高まります。
✅ やるべきこと
- Googleフォームなどを活用し、オンラインで回収する。
- 管理職や教育委員会の意向に沿った形で、デジタル化を進める。
- どうしても紙で回収する場合は、説明会でその場で提出してもらう。
✅ ここがポイント!
→ ヒューマンエラーを防ぐために、デジタル回収を優先する。
まとめ|説明会の成功は事前準備がカギ!
✅ 連絡アプリの登録は「説明会で完了」させる。
✅ 地区班の確認は、視覚化と対話の場を作って確実に行う。
✅ 幼児対策をしっかりして、説明会の進行をスムーズにする。
✅ 結核関係の書類は、可能なら事前に回収する。
✅ 個人情報の回収は、オンライン化して紛失リスクを減らす。
説明会の場でできることは、その場で終わらせる!
そうすることで、新年度の混乱を減らし、スムーズなスタートが切れます。
「やっておいてよかった!」と思える準備を進めていきましょう!
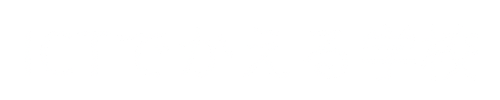



コメント