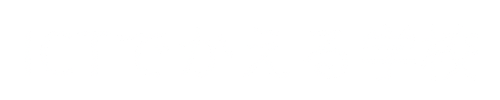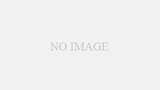学校の先生方は、授業や教材作成の中で多くの著作物を利用する機会があります。しかし、「これは著作権に触れるのか?」「どこまでが許されるのか?」と迷う場面も少なくないのではないでしょうか。この記事では、学校現場での著作権の基本的な考え方と、守るべきポイントについて、具体例を交えて分かりやすく解説します。
まずは著作権の基本を知ろう
著作権は、著作者が自分の作品を守るための権利です。簡単に言うと、「作品を作った人がその作品をどう使うかを決める権利」を持っているということです。だから「どう使おうがオレの自由だろ」ならないのです。
基本的に次の2つを意識することで、著作権を守りながら著作物の利用がしやすくなります。
著作者の利益を守る
著作者が作品を通じて得るべき利益を損ねないようにすること。
以前、一人一台iPadが配布された時に、子供達にこのように指導をしたことがあります。
「もしも〇〇さんが好きなマンガをiPadで全部写真に撮って「これ超面白いから送るねー」と1冊分丸々、友達みんなにばら撒いたとするね。その漫画の作者があなたの家族です。本当ならみんなに買ってもらって読んでもらうことによってあなたのお家の生活費になる予定でした。でもこの行為のせいでそのお金がなくなってしまったり減ってしまったりしたとしたら?」と。
多くの作品は、作者の生活を支えていると考えるとその収入源がなくなってしまう事がどれだけ迷惑なことかということなのです。法律だから、と一言で言うこともできますが、具体的な事例や例え話を織り交ぜながら指導するとイメージがつきやすくなります。
著作者の思いを大切にする
作品の意図を歪めたり、改変によって著作者の名誉を傷つけないこと。
これらを意識するだけで、著作物を適切に扱える第一歩となります。
例えば、自分の作品が勝手にアダルトサイトや犯罪サイトに使われていたとしたらイヤですよね。そういう目的で作ったのではないのに意図に反して使われることは著作者にとってとても不快極まりないはずです。
「そんな意図で作ったんじゃないわい!これは自分の作品に対する侮辱だ(怒)訴えてやる!」
となるわけです。
教育現場における特例:授業での利用
実は、教育現場では著作権法に特例が設けられています。これを知っておくと、安心して授業に著作物を活用できます。
教育目的であれば著作権料なしで利用できる
教室で授業のために本や映像、音楽を使う場合、非営利であれば著作権料を支払わずに利用できる場合があります。
• 例: 授業中に市販の本を生徒に見せる、CDを授業で流す。
必要最低限のコピーはOK
授業のために教科書や参考書の一部をコピーして配布することは、教育目的であれば認められることが多いです。ただし、コピーは「必要最低限」に抑える必要があります。
• 例: 問題集の一部を抜粋してプリントにするのはOK、すべてのページをコピーするのはNG。
オンライン利用には注意
オンライン授業やデジタル教材では、著作物をネットに配信することが伴うため、許可が必要になる場合があります。
• 例: 授業動画に市販の音楽や映像を使用する場合、その部分をカットするか許可を得る必要がある。
著作物利用の基準:迷わないための4つの視点
先生方が著作物を使うときに迷った場合、この基準を参考にすると判断しやすくなります。
利用目的を確認する
授業や教材作成など、教育目的で非営利の場合は基本的に安心して利用できます。ただし、営利目的や学校外での利用は注意が必要です。
範囲を確認する
著作物を利用する範囲を最小限に抑えることが重要です。必要な部分だけを使用することで、著作権侵害のリスクを下げられます。
共有方法に気をつける
教室内での利用は問題になりにくいですが、インターネット上に公開する場合は著作権者の許可が必要になることが多いです。
出典を明記する
引用を利用する場合、出典を明確に示すことで、トラブルを回避できます。引用する場合は自分の文章が主で、引用部分は補助的であることが条件です。
具体例で見る著作権の判断
実際の授業でどのように著作物を利用できるか、具体例で確認してみましょう。
例1:教室での本や映像の利用
• OK: 市販の本や映像を授業で生徒に見せる。
• NG: 映像や本をデジタル化して生徒に配布する。
例2:画像やイラストの利用
• OK: フリー素材サイト(PixabayやUnsplash)の画像を利用する。
• NG: Google画像検索で見つけた画像を無断で使用する。
例3:音楽の利用
• OK: 授業内で市販の音楽を流す。
• NG: 授業動画に市販の音楽を含めたままオンライン配信する。
実践のためのヒント:フリー素材を活用しよう
著作権に配慮しつつ、授業を充実させるためには、フリー素材や公認教材を活用するのもおすすめです。フリー素材と謳われているものでも、必ず利用規約で使用の目的や範囲、条件などは確認しておくことで、万が一の権利侵害の予防になります。
先生のための著作権第一歩
著作権は複雑に見えるかもしれませんが、「著作者の利益を守る」「著作者の思いを大切にする」という基本を意識すれば、迷わず利用できます。また、教育現場に特例があることを知り、適切な範囲内で利用することで、安心して授業を進めることができます。
私のパパ友に弁護士の方がいるので、著作権について雑談で伺ったことがあるんです。その時に言われたのが「著作権裁判は明確な答えがない、確実にOKとはなかなか言い切れない分野。大丈夫だと思っていても著作者側の主張によって著作権侵害となった例もある。」と言われました。
「元も子もないなぁ」と思いつつも、改めて自分が著作者だったらということを考えることが最も大切なことなんだろうなと思いました。
著作権とは著作者を守る権利ですから、
「こんな使い方されちゃ困るんだよなぁ。」
と作った側の人が思うかどうか、それは人によってちがうわけです。
まずは著作物により、生計を立ててると考えればその金銭的な不利益を生じさせないという基準が考えられますよね。
想いを込めて時間をかけて作ったものだとしたら、それを台無しにされるような使い方をされたら怒りますよね。
「お金と心の不利益」
この2つがポイントになると、著作権について私が調べた結論です。これを意識して授業の特例の有無に関わらず日々自分はもちろん子供の指導もしています。
最後に改めて、記事の中でお伝えしたように著作権については明確な答えはありません。また、日々社会と共に変わり続けています。
今回お示しした指標は、あくまで私が個人で学んだことから結論づけたものです。
まずは今一度自分でも学んでいただくきっかけにしていただけたら嬉しいです。その上で著作物の利用や子供達への指導などにあたっていただけたらと思います。
下記は私が以前、著作権フリーの教材を探していた時にまとめたスライドです。
お役に立てれば幸いです。その際には必ず使用前には利用規約をご確認ください。
※本記事は筆者の学びや経験をもとにした個人の見解となります。この記事の内容による著作権に関する事故などにつきましては、一切の責任は取りかねますので自己責任でご活用ください。作県の指導について考えるきっかけにしていただければ幸いです。