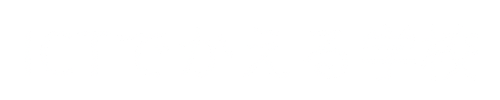子どもがふと「なぜ学校に行くの?」と問いかけたとき、頭に浮かぶのは「社会性」という言葉かもしれません。私が考える学校に通う意味は、次の三つの要素に集約されます。

もちろん、知識や学力の習得は大切ですが、学校が本当に提供しているのは「人とのリアルな関わり」です。オンライン学習が普及している現代だからこそ、対面での交流が育む協調性や自己表現、そして、忍耐力の価値は計り知れません。
多様な価値観との衝突と協調

学校は、さまざまな背景や意見を持つ仲間たちと出会う場所です。その中で、子どもたちは無作為に組み合わされたクラスや出会いの中で、自分とは異なる考え方や生活様式に触れ、時には意見の衝突や葛藤を経験します。これらの経験は、他者の話に耳を傾け、共に問題を解決していく協調性を養う絶好の機会となります。オンライン環境では、こうしたリアルな意見交換や感情のぶつかり合いが得られにくいのです。
我慢と忍耐―成長への試練

学校生活は、時に自分の思い通りにならない現実と直面させ、子どもたちに「我慢する力」を教えます。教室ではお馴染みの「整列」や「全員が前を見て座る」というのも日常の中での一幕です。自分のしたいことと、今しなければならないことの小さな衝突や摩擦を乗り越える過程で、自己の感情をコントロールし、困難に立ち向かう方法を学んでいきます。こうした体験は、家庭やデジタルな学びではなかなか味わえない、心の強さ(レジリエンス)を育む大切な要素です。
自己表現と個性の輝き

授業や部活動、学校行事といった多様なシーンで、子どもたちは自分の考えや感情を自由に表現する機会に恵まれます。対面のコミュニケーションは、微妙な表情や声のトーンを感じ取りながら、深い自己理解と他者理解を促します。個性を発揮するということは、単なる自己主張に留まらず、社会のルールを守りつつ自分らしさを表現するという、成熟した判断力の現れでもあります。
感情の交流―心が育む成長

教室での何気ない会話、廊下でのふとした触れ合い、放課後の仲間との絆…こうしたリアルな感情の交流は、子どもたちの自己肯定感や安心感を育む大切な財産です。直接会って語り合うことで感じる温かみや臨場感は、画面越しのコミュニケーションでは得難いものです。
学校がもたらす未来への可能性

現代社会では、情報技術の進化により学びの形は多様化しています。しかし、心と心が直接触れ合うことでしか得られない経験や成長もまた存在します。学校は、知識の詰め込みだけではなく、実際の人間関係や摩擦を通じて、子どもたちが自分自身と向き合い、他者と共に成長するための「実践の場」として機能しています。小さな社会としての学校での体験は、将来の進路選択や社会生活に不可欠な視野と柔軟な思考を育み、可能性の扉を広げるのです。
おわりに

私たち大人は、技術がどれほど進化しても、直接人と触れ合うことの価値を決して見失ってはなりません。学校での体験は、知識を超えた人間的な成長を促し、未来への希望と挑戦の象徴です。子どもたちがルールの中で自由に自己表現し、互いに支え合いながら成長する姿は、私たち大人にとっても大きな励みとなります。これからも、学校というかけがえのない環境を守り、次世代がその可能性を最大限に発揮できる未来を築いていく責任があると信じています。
おまけ「リアルと仮想空間はどこまで近づくことができるか」

メタバース空間と対面学校生活の融合
近年、VRゴーグル、ARグラス、ハプティックデバイス、アロマデバイスなどの先端技術が飛躍的に進化し、メタバース空間での学習体験が実際の教室に近づいています。例えば、以下のような製品がその代表例です。
これらのデバイスは、視覚や聴覚に加え、触覚や嗅覚までをも再現することで、遠隔地にいながらも臨場感あふれる対面授業の再現できる時代もそう遠くないのかもしれません。
society5.0のイメージ動画でも仮想空間がよりリアルになることがアピールされています。
これらの技術革新により、対面授業に匹敵する交流や学習体験が可能となる一方、非言語コミュニケーションや偶発的な交流の再現など、解決すべき課題も残されています。しかし、今後の発展により、より自然で充実した教育環境が実現されることが期待できそうですね。