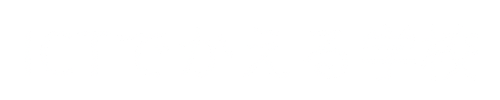「デジタル機器の使いすぎで学力低下」
「スマホ漬けの子どもたち」
こんな見出しを、ニュースやネットで目にすることが多いですよね。しかし、私はそうした警鐘を鳴らす声に対して違和感を抱いてきました。コロナ禍以降、学校現場でICT推進を担当する中で、子どもたちの未来を考えたときに浮かんだのは、単に「デジタルを使わせる・使わせない」という二項対立ではないということ。
本当に大切なのは、AIやテクノロジーを正しく使いこなす“心”を育てることです。
■ デジタル機器がもたらした変化と課題
現代の子どもたちを取り巻く環境は、かつてとは大きく異なります。
電車に乗れば大人も子どももスマホに夢中。
家庭でも、親は自分のスマホを眺めながら、子どもにはタブレットを渡して静かにさせる。
友達同士で集まっても、目の前の会話よりSNSの通知が気になる。
子どもたちは、大人たちの姿を見て育っています。
どれだけ「デジタルは悪だ」と教えても、大人自身がスマホに依存している姿を見せていては、説得力がありません。
小学校と家庭でのAI活用の現場
小学校でのAI活用の具体例
職員室である先生が、「AIって、結局一般的なことしかできないから人間がやらなくちゃいけないんだよね。」と話したことがありました。
そのとき私は、「まさにその通りです。でも、AIはすべてを自動化するわけではなく、途中の段階をアシストしてくれるんですよ」と答えました。
AIは、単純作業や情報収集、データの整理などは効率的に処理できるますが、最終的な決定や内容のチェックは人間の役割なのです。
実際に、私たちの現場でもAIの導入によって多くの業務が効率化されました
- Google Chatへの自動通知
- ポータルサイトの作成と運用
- 電子保健板の自動更新
- 授業の振り返りへのフィードバック生成
これらはプログラミングスキルがほぼゼロでも、AIと協働することで具現化できた事例てす。
結果的に、ICT支援員に頼らずとも現場でシステムを作成し、業務ツールを開発することが可能になりました。
働き方改革や人手不足が進む今、AI導入の重要性はさらに高まっています。
家庭でのAI活用の具体例
家庭でも、AIはさまざまな場面で役立っています。
例えば、画像生成を使って子どもの自由研究のサポートをしたり、調べ物を効率化することで、家庭学習の質を向上させることができました。
また、家庭では家族の役割分担表や子どもの評価の見直しなど、AIを活用して家庭内のコミュニケーションの改善にも貢献しています。
AIの柔軟な活用で、家庭の課題解決や日常のルーティン改善にも大きな効果が見られました。
デジタルを正しく使うために大切なのは「道徳」
ICT教育を進める中で、私が常に軸に据えているものがある。
それは、「道徳」です。
- 相手を思いやる心
- 誰かの役に立ちたいという気持ち
- 人を傷つけない優しさ
- 正しいことを見極める倫理観
AIは、私たちが入力するプロンプト(指示)に対して最適な回答を返してくれます。
ですが、そのプロンプト自体が他人を傷つける意図であったり、不誠実な行動を助長するようなものであったらどうでしょうか?
AIは、善悪を判断することはできません。
正しい使い方を選ぶのは、あくまで“使い手”である私たち人間なのです。
教師が今こそ議論すべきこと
- AIとの共存に必要な「心」をどう育むか
- 子どもたちが“AIの使い手”になるためのマインドセット
- デジタルを「禁止」ではなく「適切に活用する」ための指導
未来を担う子どもたちの「ロールモデル」になる
最後に、私たち大人が肝に銘じるべきことがあります。
「子どもたちは、大人の言葉ではなく、行動を真似る」ということです。
AIやテクノロジーと正しく付き合うロールモデルになること。
それこそが、これからの教師に求められる役割ではないでしょうか。
AI時代に必要なのは「心の教育」
AIやテクノロジーが急速に進化する中で、求められるのは「使いこなすスキル」だけではたりません。
大切なのは、その使い方を正しく導く“心”を育てることです。
これからの教育現場では、AIを活用しながらも、思いやりや倫理観を大切にする心を育てていくことが、教師の最も重要な使命になるでしょう。
「AIを使いこなせる子ども」ではなく、「AIと共により良い未来を築ける子ども」を育てること。
それが、私たち教育者に求められている“新しい道徳教育”なのです。